鯉って実は外来種って知ってた?意外と知らない鯉の生態について解説します。
鯉と聞くと、色鮮やかな錦鯉を思い浮かべる方がほとんどなのではないでしょうか。
その錦鯉はよく庭園などを泳いでいるため、いかにも日本というイメージがありますが、実は外来種です。
しかし、国内には在来種の鯉もちゃんと存在しています。
今回は、そんな鯉について解説していきます。
在来種の鯉について

在来種『野鯉』
日本には、在来種の鯉も存在しています。
その鯉は「野鯉(のごい)」という名前で、主に琵琶湖に生息しています。
琵琶湖の他にも霞ヶ浦などに生息していると言われていますが、はっきりとしたことは分かっていません。
そのため、近くの川で鯉を見かけた場合は、野鯉である可能性は限りなくゼロに近いでしょう。
野鯉の生態
体長:60〜90cm
寿命:約20年
その体は、良く見かける錦鯉とは異なり、細長い姿をしています。
そして、野鯉は水深が30m以上ある比較的深い場所に生息していると言われています。
食性は何でも食べる雑食で、貝や藻を食べています。
鯉には歯が無さそうなのに、貝なんてどうやって食べるんだろうと疑問に思ったそこのあなた。安心してください。
鯉は喉に強力な歯を有しており、この歯を使って貝などを噛み砕くことができるのです。歯が無いと思ったあなたは鯉に謝りましょう。笑
外来種の鯉について
大和鯉は養殖用
大和という、いかにも日本の鯉だという主張が強い大和鯉ですが、実は外来種です。
なぜ大和鯉と呼ばれているかと言うと、昔は大和という地で養殖されていた鯉のことを大和鯉と呼んでいて、それが段々と養殖の鯉全般を大和鯉と呼ぶようになったと言われています。
錦鯉は観賞用
錦鯉といえば、庭園の池などで優雅に泳いでいる姿が容易に想像できると思います。
この錦鯉も外来種です。
錦鯉といえば、赤や白、黄色など、色鮮やかな体色が特徴で、販売価格は数万円から、体色の綺麗な個体で数十万円する錦鯉もいます。
鯉の生態

体の特徴
ここからは、全般的な鯉の生態をお話ししていきます。
鯉の特徴的な生態として、まず挙げられるのが、鯉には胃がないということです。
鯉は、エサを食べると、食道を通った後、胃がないため、そのまま腸にいきます。
胃で食べたものを蓄えることができないため、継続的にエサを食べる必要があります。
胃が無い分、鯉の腸は他の魚に比べて、長くできています。
鯉は何でも食べる雑食
前述したとおり、鯉は何でも食べる雑食です。
貝や藻など水中にあるものから、ユスリカなどの小型の昆虫、水の中に落ちた果物など、ありとあらゆるものを食べます。
何でも構わず食べるので、あんなに大きくなるのでしょうか。鯉のエサやりをした経験がある方は想像していただけると思いますが、エサへの執着心がものすごいです。
時には他の鯉の上に覆い被さるように鯉が乗り上げることもあります。ここまで純粋に欲を出されると、見ていて可愛いですよ。
鯉の一生
鯉は、春から夏にかけて産卵を行います。
鯉の産卵は藻が多い浅瀬で行われ、1匹のメスに複数匹のオスがもみくちゃになって行われます。
ちなみに、1回の産卵で産み落とされる卵の数は50万粒にもなるそうです。すごい量ですね。
産卵によって藻に産み落とされた卵は、直径2mm程度で非常に小さい卵です。
卵はおよそ3〜6日で孵化します。
孵化したばかりの鯉は体長約5mmと小さいですが、ちゃんと魚の形をしています。
その後、鯉はたくさんエサを食べ、2〜3年で成熟し、産卵を行うことができます。
まとめ:鯉を眺めて優雅な気持ちに
いかがでしたか。錦鯉がまさか外来種だとは驚きでしたよね。他にも喉に歯があったり、胃が無かったりと面白い特徴をたくさん持っている鯉のとりこになってきてはいませんか?この週末はそんな鯉を眺め、優雅な気持ちになってみては?それでは。
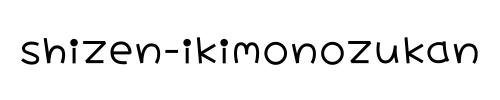







コメント