ヘビって冬はどこにいる?冬眠場所にはある共通点が!
ヘビ。暖かい時期は活発に活動しますが、冬になり、寒くなると冬眠をするため、我々の目の前から姿を消します。
では、ヘビはいったいどこで冬眠をしているのでしょうか。解説していきます。
ヘビの冬眠
ヘビはなぜ冬眠するのか
ヘビは変温動物なので、人類のように自分で体温調節ができず、外気温によって体温が変化する動物です。
そのため外気温が寒くなると、ヘビ自身の体温も低下し、活動することができなくなるので、冬眠を行うという訳です。
冬眠する温度、冬眠期間
具体的には、気温が3℃程度になる、12月から3月の間冬眠をします。
春が近づき、気温が5度を上回ってくると、ヘビは冬眠から目覚め始めます。
ただし、すぐに本調子とはいかず、気温が10℃を超えてきて活発に活動を始めます。
我々が朝起きてすぐ本調子といかないのと似ていますね。
冬眠場所
ヘビが冬眠を行う場所には共通点があります。
その共通点とは、比較的薄暗くて、寒さをしのげる場所です。
寒さをしのげる場所というと、大雑把ですが、具体的には、石の下や空き家の中、土の中などが挙げられます。
ヘビは、なるべく暖かい場所で冬眠をしようと考えているため、上記の場所を探すと、かなりの確率でヘビに遭遇できると思います。
ヘビの冬眠は眠ると言っても、仮死状態になるので、そのまま死んでしまうこともあるそうです。
場所選びは大切ですね。
ヘビの生態

ヘビは怖がり
ヘビを見ると、つい怖れて、腰を抜かしてしまいそうになりますが、実はヘビも人間を怖れています。
その根拠として、人間に遭遇したヘビは、すぐに逃げ出すか、丸まって固まる、威嚇を行うといった行動をおこします。
威嚇と言っても、噛み付いてくるわけではなく、こちらの様子を伺っているといった仕草になります。
ただ、ヘビが攻撃してこないと思って調子に乗ると、ヘビも攻撃するしかないと思い、噛み付いてきます。
下手にヘビを挑発しないように気をつけましょう。
以上、ヘビは怖がりで自分からは攻撃してこないと言いましたが、一つだけ例外があります。
それは、捕食行動を取る場合です。
いくら自分から攻撃をしてこないとは言っても、食料を手に入れるためとなると話が変わります。
そのため、ヘビが捕食対象としているカエルなどを触った手でヘビに近づくと、カエルの匂いを察知し、勘違いで噛みついてくることがあります。
カエルなどヘビの捕食対象の動物を触った後は、しっかりと手洗いをするなど、匂いを消しましょう。
蛇の捕食対象
ヘビは主に、カエルや魚、鳥、ネズミなどを捕食対象としています。
全てのヘビが上記の生き物を好んで食べている訳ではなく、ヘビの種類によって食べているものが異なると言われています。
例を挙げると、アオダイショウは木に登ることが得意なため、鳥を捕食することが多く、マムシは地上でカエルやネズミを捕食していることが多いです。
ヘビの感覚器官

蛇だけがもつピット器官は熱を感知する
蛇は、視覚や聴覚、嗅覚など生き物が持っている感覚器官を持っていますが、ヘビ特有のものとして、ピット器官と呼ばれるものがあります。
初めて聞いたという方も多いと思いますが、どのような器官なのでしょうか。
ピット器官は目と鼻のちょうど真ん中付近にある熱を感じることができる器官です。
この器官は優れもので、少しの熱でも感知することができます。
このピット器官を使って、物事を判断しているという訳ですね。
まとめ:ヘビの冬眠は命がけ
いかがでしたか。ヘビは変温動物なため、寒くなると冬眠をする必要があること、その冬眠場所を誤ると、死んでしまう可能性もあることが分かってもらえたと思います。他にも、ヘビは怖がりという愛くるしい一面もあるヘビのとりこになっているのではないでしょうか。この週末はヘビに会いに動物園に行ってみてはいかがですか。それでは。
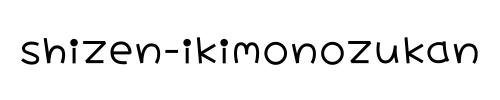







コメント